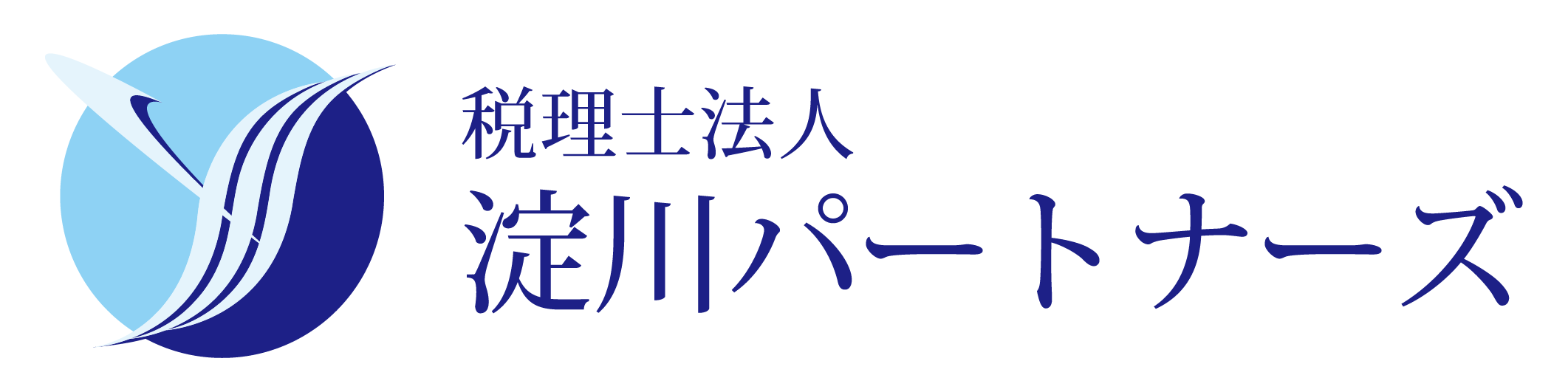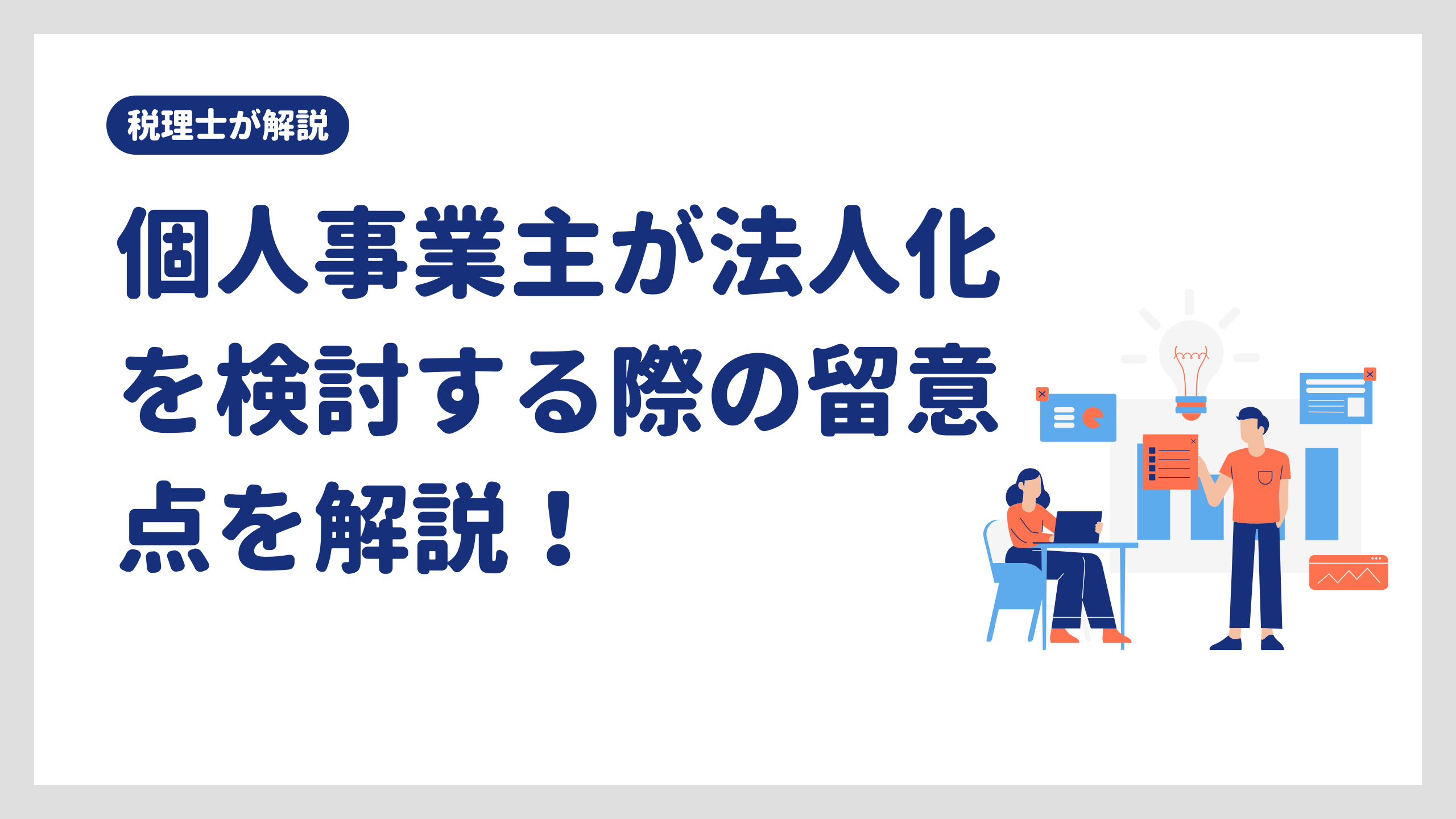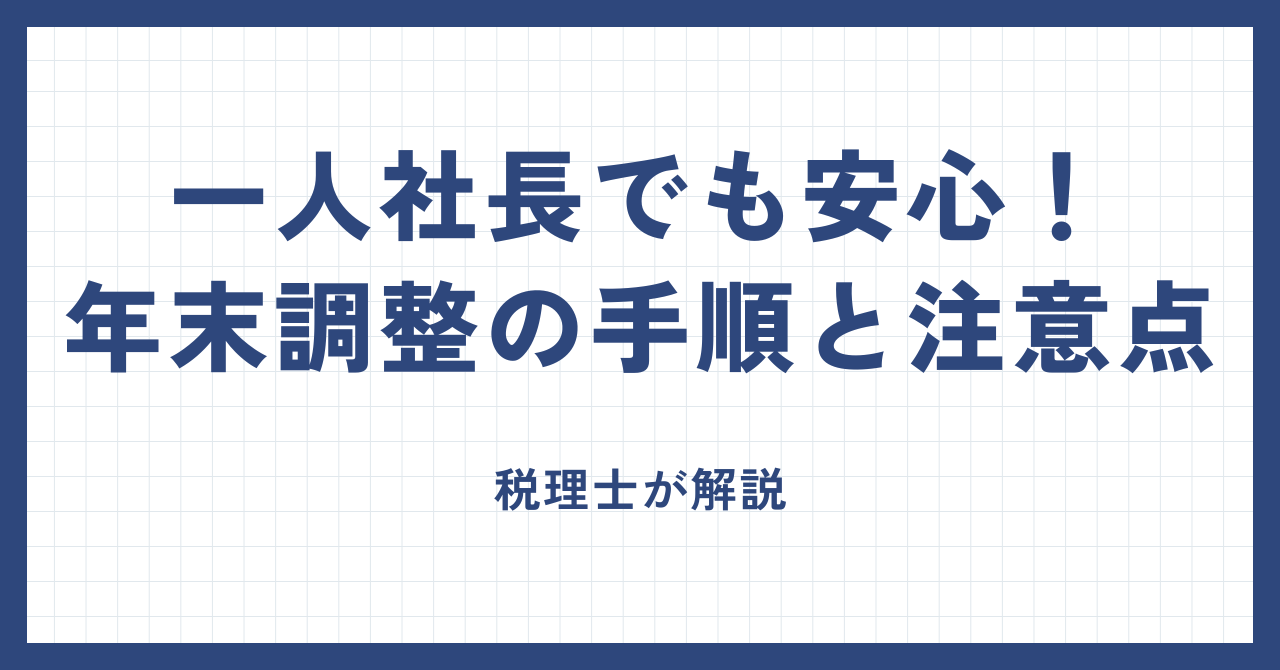【令和7年度税制改正】配偶者控除・配偶者特別控除が拡大!103万円の壁はどう変わる?
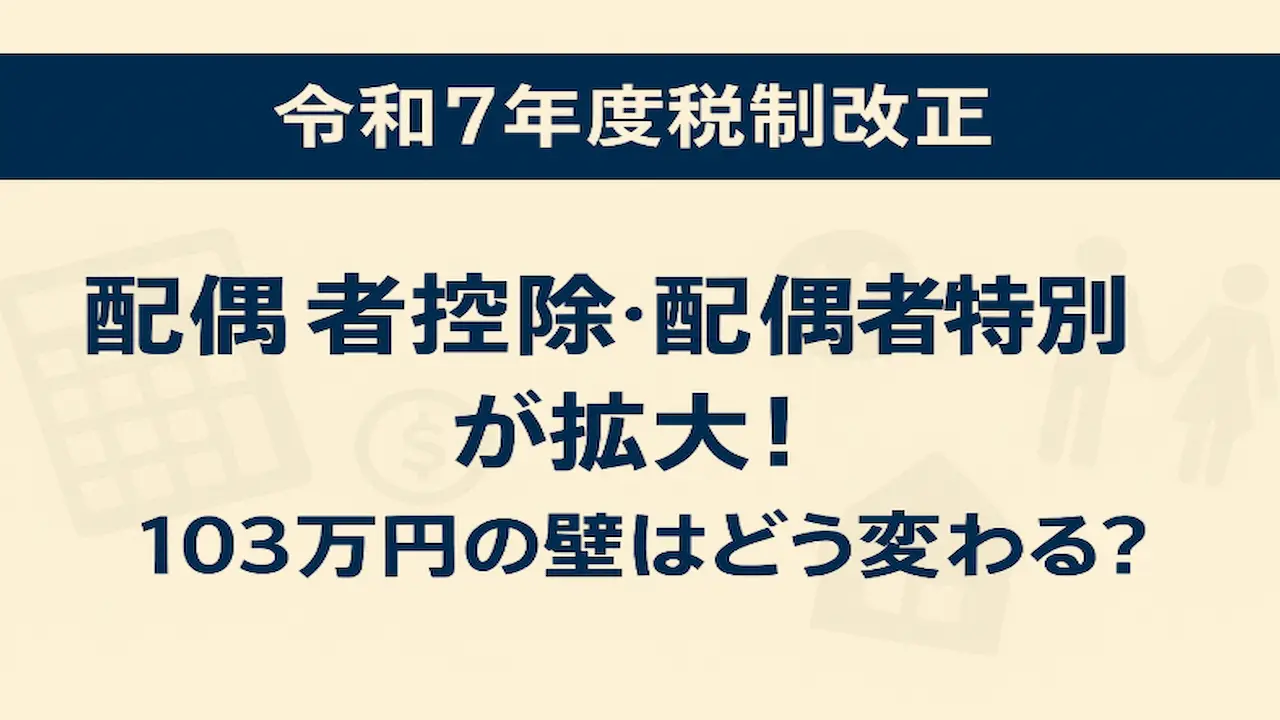
扶養控除や配偶者控除は、多くの共働き・パート家庭で「年収の壁」として意識される制度です。
令和7年度(2025年分)から所得税制度が大きく変わり、配偶者控除・配偶者特別控除も見直されます。
本記事ではまず「配偶者控除とは何か」を整理し、改正で何が変わるか、配偶者特別控除との違いや具体的な金額まで、実務上見落としがちなポイントも含めて解説します。
なお、その他の改正内容についてはこちらで解説しています。
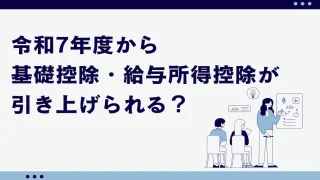
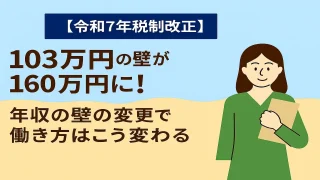
配偶者控除とは何か
配偶者控除は、納税者本人が生計を一にする配偶者(法律上の配偶者)を扶養している場合に、一定の所得控除を受けられる制度です。
所得から一定額を差し引けるため、課税所得が下がり所得税の負担が軽くなります。
主な適用条件として、配偶者が一定の所得以下であること、納税者本人の所得が一定水準以下であること、配偶者が事業専従者でないことなどが挙げられます。
従来(改正前)は、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(給与所得ベースで年収約103万円以下)であれば配偶者控除が適用される仕組みでした。
一方で、配偶者の所得が48万円を超える場合には「配偶者特別控除」が適用されます。
配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象外となる所得水準であっても、段階的に所得控除を受けられる制度です。
令和7年改正で変わる要件
令和7年度の税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除の要件が次のように見直されます。
所得要件の引き上げ
改正前は配偶者の所得要件 48万円以下でしたが、改正後は 58万円以下 へ引き上げられます。
これにより、給与所得ベースでは年収 123万円以下 までが控除対象となります。
また、扶養親族や同一生計配偶者に対する所得要件も、48万円から58万円に引き上げられます。

配偶者特別控除の「満額適用」年収上限引き上げ
従来、配偶者特別控除で満額(配偶者控除と同額)の控除を受けられる上限が年収 150万円程度でしたが、改正後は 160万円 に引き上げられる点も制度変更点です。
つまり、配偶者の年収が160万円以下であれば、配偶者控除と同等の控除が可能となります。
また、配偶者特別控除の適用範囲にも改正が加わります。
配偶者控除・配偶者特別控除の具体的な控除額
改正後の配偶者控除・特別控除における控除額は、納税者本人の所得金額によって段階的に変わります。
改正前後の変化を踏まえた代表的な控除額例は次の通りです。
| 区分 | 控除対象配偶者の所得上限 | 控除額の目安* |
|---|---|---|
| 配偶者控除(満額) | 所得58万円以下(給与年収123万円以下) | 一般控除:38万円 |
| 配偶者特別控除で満額適用 | 所得58万円超 ~ 133万円以下 | 最大で38万円 |
実際の控除額は、納税者本人の所得や他の控除適用によって異なります。
実務上の留意点と注意点
- 控除上限が拡大したとはいえ、配偶者の年収が高くなると、控除額は逓減する区分に入るリスクがあります。特に本人の所得が高い場合は控除額に制限がかかることがあります。
- 制度改正は所得税上の改正であり、住民税・社会保険や扶養認定制度では適用タイミングや基準が異なる場合があります。
まとめ
令和7年度の所得税制度改正で、配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件引き上げと控除対象年収の拡大が行われ、「103万円の壁」が実質「123万円」「160万円」の壁へ変動しました。
制度改正によって、配偶者の就労範囲に余裕ができる世帯も増えると見込まれます。
ただし、控除額の逓減・所得制限、住民税・社会保険制度との関係など、複数の観点での確認が欠かせません。
私たち「淀川パートナーズ」は、税務顧問や経理事務の効率化など幅広く対応しています。