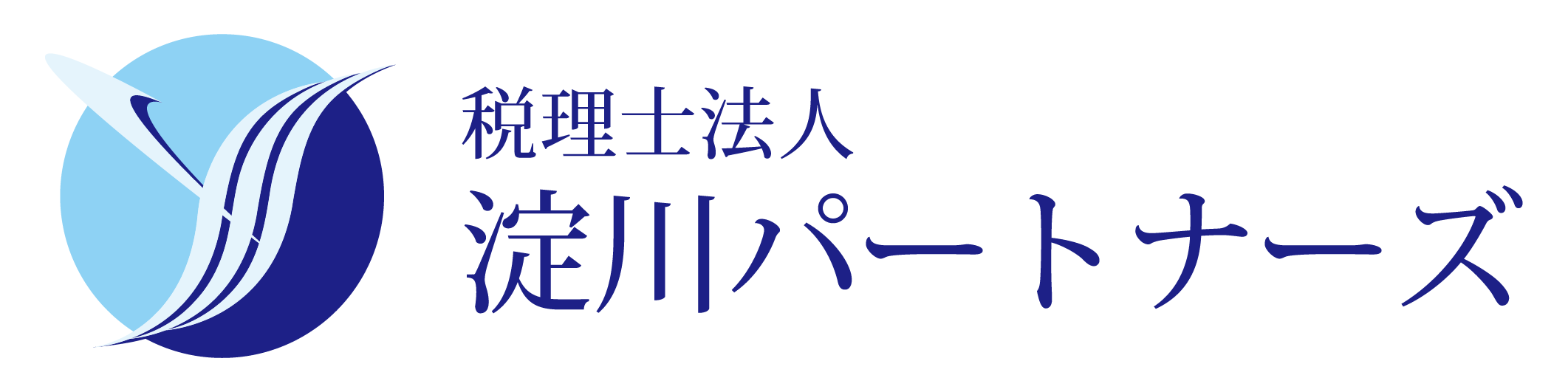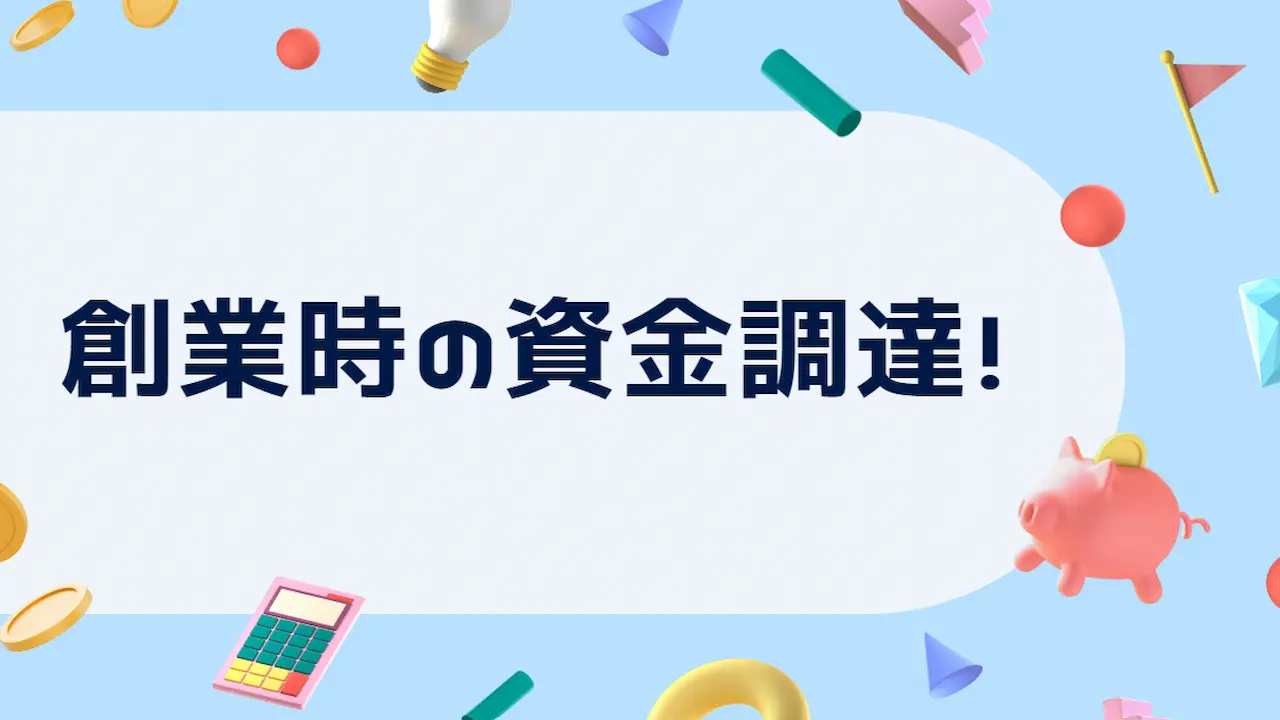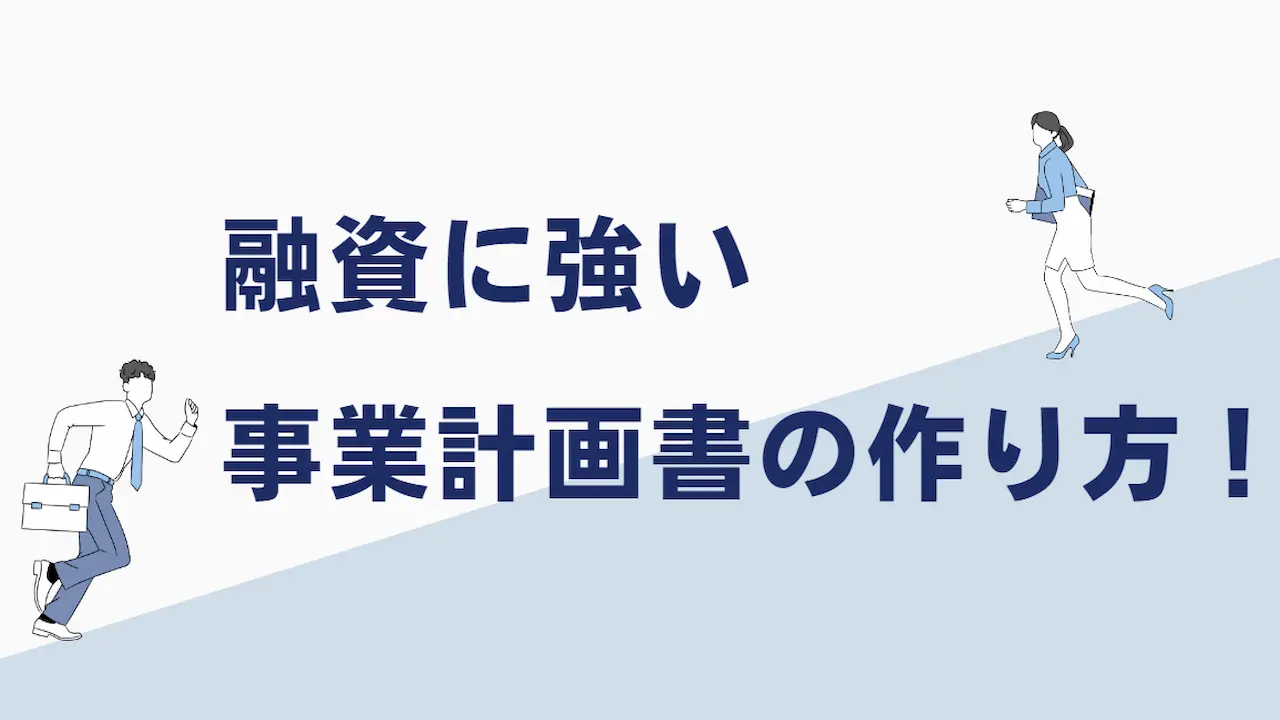【起業家必見】創業融資のリスクとは?失敗しないためのポイントを解説!
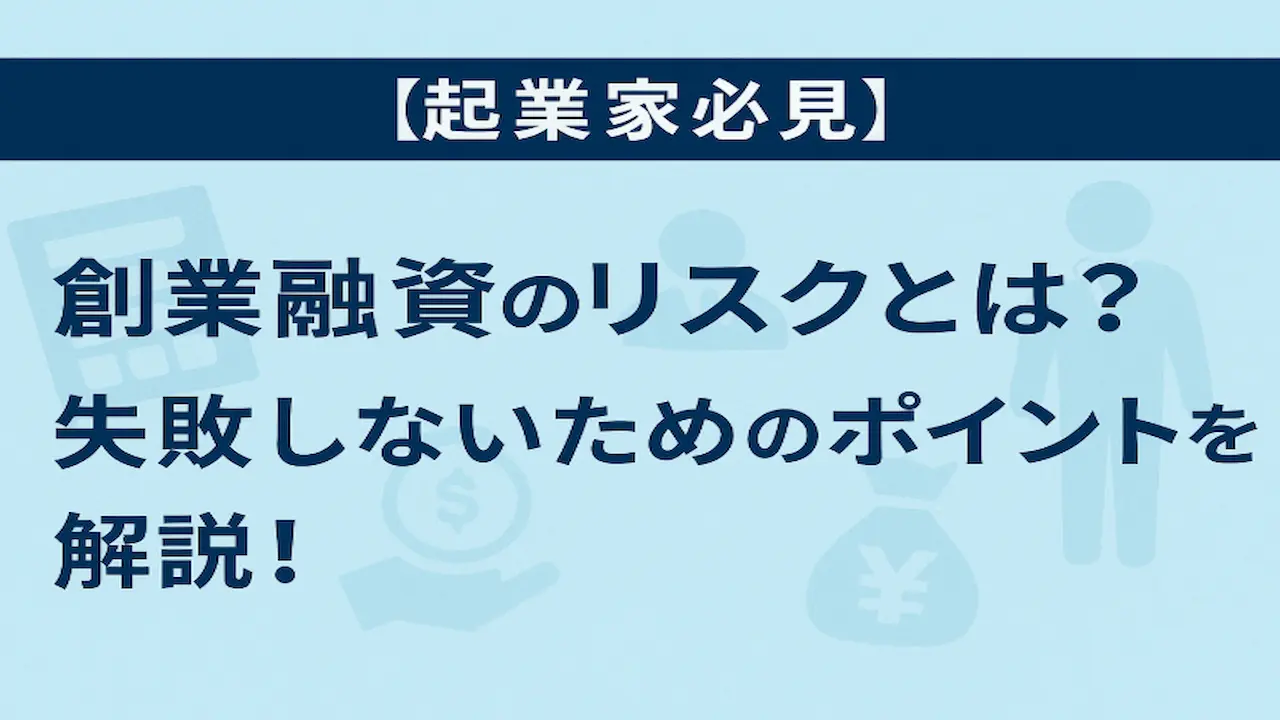
起業を考える方にとって、創業融資は資金調達の大きな選択肢です。
中でも「日本政策金融公庫」の創業融資は、無担保・無保証で利用できることもあり、非常に人気があります。
しかし、創業融資にはメリットだけでなく、リスクも存在します。
この記事では、創業融資の基本から、起業家が注意すべきリスクとその対策を具体的に解説します。
なお、日本政策金融公庫の概要やメリットについてはこちらで解説しています。


創業融資とは
創業融資とは、これから事業を始める人や、開業して間もない人を対象にした融資制度です。
開業に必要な設備資金や運転資金を、銀行や日本政策金融公庫などから借り入れることができます。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は代表的な制度で、
- 無担保・無保証で借りられる
- 創業から2年以内でも利用できる
といった特徴があります。
しかし、審査を通過するには事業計画の信頼性や返済能力が重視されるため、しっかりと準備をして臨むことが重要です。
詳細は、日本政策金融公庫のHPをご確認ください。
創業融資に潜む主なリスクとその対策
1. 借りすぎによる返済負担のリスク
事業を始める際、将来の成長を見越して多めに資金を借りるケースがあります。
しかし、売上が計画通りに伸びなかった場合、返済負担が経営を圧迫し、資金繰りが悪化するリスクがあります。
対策: 事業計画をもとに「必要資金」と「返済可能額」を明確に分けて考えましょう。特に日本政策金融公庫の融資では、過剰借入はマイナス評価となることもあるため、現実的な借入額を設定することが重要です。
2. 審査落ちのリスク
創業融資の審査では、事業計画書の内容や自己資金、経歴などが詳細にチェックされます。
経験不足や準備不足により、融資審査に通らないケースも少なくありません。
対策: 審査のポイントを理解し、採算性・実現可能性の高い事業計画書を作成しましょう。税理士や専門家のアドバイスを受けることで、通過率を大きく高めることができます。
3. 返済不能に陥るリスク
予期せぬ売上減少や取引先の倒産などで資金繰りが悪化し、返済できなくなるケースがあります。
特に創業初期はキャッシュフローが不安定なため、返済不能は致命的なリスクです。
対策: 売上が想定より下回った場合を想定し、返済計画を複数パターン用意しておくことが大切です。また、融資額の一部を「緊急時の予備資金」として確保しておくことも有効です。
4. 資金使途の誤りによる信用低下のリスク
融資資金を本来の目的以外に使うと、金融機関からの信用を失う可能性があります。
例えば、設備資金として借りたものを運転資金に回すなどのケースは避けなければなりません。
対策: 資金用途は明確にし、事業計画書に沿った支出を行いましょう。支出の根拠となる領収書や見積書を保存しておくことで、後の説明もスムーズに行えます。
5. 追加融資が受けられなくなるリスク
創業融資後に資金が不足しても、追加融資が認められないケースがあります。
特に、初回融資の返済状況や資金の使い方が不適切だった場合、信用が低下します。
対策: 融資後も定期的に資金繰り表を作成し、早期に課題を発見できる体制を整えましょう。資金繰りの悪化が見込まれる場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。
6. 創業計画の見通しが甘いリスク
創業直後は、思ったように売上が上がらなかったり、想定外の費用が発生することがあります。
計画段階で甘い見通しを立ててしまうと、早期に資金ショートする危険性があります。
対策: 事業計画書を作成する際は、売上予測を楽観的にせず、最悪のケースを想定して試算することが大切です。経験豊富な税理士のチェックを受けることで、より現実的な計画になります。
リスクを理解し、堅実な資金計画を
創業融資は事業のスタートを後押しする強力な手段ですが、リスクを理解せずに進めると経営に大きな影響を与えます。
特に借入額の設定や返済計画、資金管理は慎重に検討する必要があります。
融資を受ける前に、事業計画の内容や資金繰りを専門家と一緒に確認し、無理のない範囲で資金調達を行うことが、成功への第一歩です。
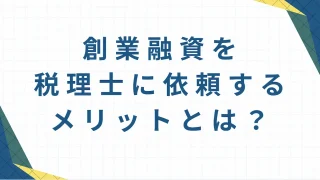
まとめ
創業融資には「借りすぎ」「審査落ち」「返済不能」などのリスクがありますが、事前に準備と対策を講じることで大きく軽減できます。
私たち税理士法人淀川パートナーズは、日本政策金融公庫の創業融資支援に多くの実績がある税理士法人として、資金調達から開業後の経営サポートまで一貫して支援しています。
融資を受けたいけれど「何から始めればよいかわからない」「審査に通るか不安」という方も、ぜひ一度ご相談ください。
これまでの支援経験をもとに、あなたの事業に最適な資金調達方法を、専門家がわかりやすくご提案いたします。